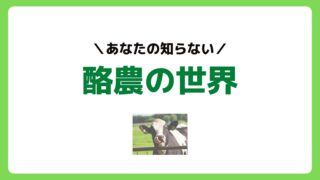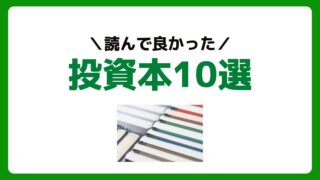インドの独立運動を主導した、非暴力・不服従で有名な「マハトマ・ガンディー」について書かれた本です。
ガンディーに関しては、多くの方が歴史の授業で習っているでしょう。
しかし、教科書にさらっと書かれている印象からは、また違ったガンディー像について本書を読むことで気づけるはずです。
読んだ印象として、特に次のような方におすすめの本でした。
- ガンディーの生涯について知りたい
- イギリス支配下のインドの様子を知りたい
- インドにおけるヒンドゥー教とイスラム教間の摩擦について知りたい
本書を読んだきっかけ:教科書のイメージからくるガンディー像は違う
本書を読んだきっかけは、歴史系ポッドキャスト番組の「COTEN RADIO」にてガンディーの生涯を知ったこと。
同時代に生きたドイツのヒトラーと対照的な存在として紹介され、強く印象に残っていました。
ヒトラーは「怒り」を原動力とした一方、ガンディーは「愛」を原動力としてその生涯を送ったというのです。
歴史の授業で習ったガンディー像から、私自身は
「非暴力・不服従によりじっとイギリスの支配に耐えた偉人とされる人」
という印象を持っていましたが、これがどうも違いました。
たしかに非暴力・不服従でしたが、「抵抗するための活動」は積極的にしていたのですね。
こうした意外な点をコテンラジオで知りました。
そして、その生涯についてもっと知りたいとの思いが沸き、本書を手に取った次第です。
大まかな内容

本書のおおまかな内容は、
- ガンディーの生い立ち
- イギリス留学
- 南アフリカでの苦労
- サティヤーグラハ(真理の堅持)運動
- 支配者たるイギリス側との交渉
- イスラム教徒との複雑な関係
- ガンディーの死
などです。
ガンディーの生涯について全般的な内容が書かれています。
印象的だった部分
- ガンディーの生涯において随所で実施される断食がもたらす周囲への影響
- イギリスとインドという支配・被支配における理不尽さ
- 宗教にまつわる紛争の苛烈さ(カルカッタの虐殺など)
雑感
すごく感動したとか、全然面白くなかったとかいうこともなく、無難にガンディーの生涯を追っていったという印象の本でした。
概ねコテンラジオで聞いていた通りのガンディーの生涯だったため、特別な発見はなかったと言えます。
とはいえ、イギリス支配下のインドが如何に辛酸をなめていたかという点は印象的。現在でいえばロシア・ウクライナの問題が関連して想起されます。かなり考えさせられる部分がありました。
また、ヒンドゥー教とイスラム教間の摩擦についてもなかなか衝撃的でしたね。報復の連鎖が凄惨な事態を起こしていったという点は本書を読むまでは知りませんでした。そして今なお、インドとパキスタンの間でこれに関連した問題が続いています。
歴史は、過去の「終わった出来事」のみを教えてくれるだけでなく、その系譜が「今」にどう続いているかも教えてくれます。
全ての人が学ぶべきだと現実的にはとても言えませんが、より多くの人が歴史を知った方が少しでもマシな世になるのではないか。そんなことを感じました。
偉人や歴史について学ぶならオーディオブックや電子書籍が便利
偉人や歴史について知識を得たいと考えた場合、書店や図書館に紙の本を求めるのも当然良いのですが、自宅にいながら手軽に本を読む手段もあります。
- オーディオブック聴き放題サービス
- 電子書籍読み放題サービス
を利用することです。
いずれも、外に出かける必要がなく、すぐに読書ができるので大変便利です。
おすすめは以下4つのサービスです
いずれも聴き放題・読み放題の対象本がたくさんあります。
無料体験期間もあるので、短期集中で知識を身につけたいという人はぜひ活用してみてください。
↓Amazonのオーディオブックサービス「Audible」については、使ってみて非常に良かったので別途記事にしています