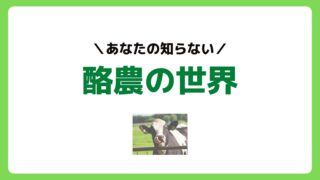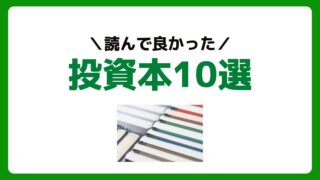米の価格高騰が続いています。最近になって落ち着きましたが、一時は野菜も小売価格が高止まりしていました。
これらの事象について、昨今のインフレと絡めて、時には陰謀論っぽいものも混じりながら、様々な言説が飛び交っているように感じます。
元酪農家として、ほとんどの言説に対して強い違和感を覚えています。もちろん私の感覚が間違っている可能性もあるのですが。
今回はこうしたことについて「元農家の目から見えているもの」を雑多に書いてみます。
米の価格高騰と「JAの暗躍」説
Xなどで現在の米価格の高騰の原因に「JAの暗躍」を挙げているものをしばしば見かけます。週刊誌の表紙にもそんな見出しを見かけました。
JA(や経済連、全農)が米の流通や価格を操作して、価格を吊り上げているとする言説です。
これについて私が思うのは、良くも悪くも「そんな力はJA、JAグループにはない」です。
農協の存在や影響力を過大評価しすぎだと思います。
私の知っているJAグループの姿は、特に2010年代の姿ですが、
- 米の流通価格低下になすすべなく、
- 「米を食べよう」と消費増のPRをするも全く効果を挙げられず、
- 日本全体の需給で決まる米の取引価格に従うだけで、
- 米農家へ支払う買取価格もとにかく「需給に従うだけ」
というものです。
当時JAが作っていた様々な資料に、米価下落になす術がないことへの理由(言い訳?)として
- 日本の人口減
- 人の胃袋の量には限りがある(人ひとりが食べる量は無限には増やせない。だから米の消費量を増やそうとしても限度がある)
- 日本人の食生活の洋食化(パンや麺の消費が増え、米が食べられなくなっている)
こんなことが書き連ねられていました。
そんなJAに、最近のような米価格の急騰をなせる影響力があるとは全く思えないのです。
農業関係で何かしら「消費者にとっておもしろくないこと」が起きると、すぐにJAはやり玉にあげられて叩かれます。その陰で農水省を含めた農政全般が多少非難されるぐらいでしょうか。
JAという存在がわかりやすいからでしょうね。
米価急騰という事態を受けて、またいつものことが起きているなというぐらいの印象です。
米農家は辛酸をなめていた
私の知っている米農家の全員が、長らく「補助金なしでは赤字の値段で米を売っている」と言っていました。
- 田の賃借料
- 種苗費
- 肥料
- トラクターの減価償却
- トラクターの修繕費
- 人件費
これらの合計額を下回る値段でしか米を売ってこれなかったということです。
その後に国からもらえる補助金によってようやく黒字になるか、品質や機械修理等なにかをミスしたら赤字になる。それぐらいの経営体が多かった印象があります。
最近がどうかは私もあまり知らないのですが、一時期のりにのっていた
- いちご狩り
- ミニトマト
- 鶏卵
- 養豚
- 肉用牛
といった業種と比べると、米農家は長い間日の目を見てこなかったのではないでしょうか。
一部の経営力のある米農家が、「JAに卸していたら経営が成り立たない」と言って
- 自社で米の販売所を作ったり(6次産業化)
- 小売業者・飲食店へ直販して、相場に左右されにくい取引単価を実現したり
といったことをしていたぐらいだと思います。
なので、たしかにここ最近の米価の急騰には一消費者としては参ってしまうものがありますが、米農家の様子を思えば「ちょっと価格変動が急すぎるけど、まあまあ・・・」と思わないこともありません。
ただし、米価の急騰分が米農家の販売収入としてちゃんと反映されていればの話ですが。
米や野菜の価格はインフレとは関係なく「単に需給」で決まっているのでは
消費者側の言説として、
- 最近の米価の高騰
- 一時期の野菜の値段の高止まり
を昨今のインフレと関連させるものが多くあります。
しかし私の考えは、「インフレの影響も少しはあるかもしれないけど、大部分は需給でしかない」というものです。
だいたいの農産物(米、野菜、肉、卵など)は市場で価格が形成されている印象が強いからです。
- 需要が強くなるか、供給が減れば「価格が上がり」
- 需要が弱くなったり、供給が増えれば「価格が下がる」
基本はこれだけだと思います。
だから「肥料価格が上がったから」とか「機械の修理価格が上がったから」といって米の値段はそうそう上がらないという気がするのです。そういうものとは関係なく、ただただ需要量と供給量だけで価格が決まっているということです。
一時期高止まりしていた野菜の小売価格が、ここ2週間ぐらいで随分と落ち着いてきたのが良い例だと思います。
私の住んでいる地域では
- 冬の間、1袋150円ぐらいだった小松菜が100円を切り
- 200円だったホウレンソウが120円になり
- 200円だったミニトマトが100円になって量も増えた
このような感じです。
本当にインフレ(機械価格、灯油・暖房費、肥料代)が反映されているなら、この価格変化は起きていないはずです。気候が良くなってきて、野菜の供給量が増えてきたから、価格が下がった。これだけだと思います。
なので、米の価格についても同じだという見方をしています。
- インバウンド需要で米の消費量が増えたから
- 近年の猛暑で米の収穫量が減ったから
- 米農家が減っていて供給量が落ちているから
- 小麦の価格上昇を受けて、消費者が急にパンや麺をやめて米を消費するようになったから
- 一部の転売業者による買い占めで米の供給が滞っているから
色んな説がありますが、私はどれも正解なんじゃないかと思っています。これら全体で米の需給がひっ迫した。だから米の価格が上がっている。こういうことなんじゃないかと。だからインフレはここではあまり関係ありません。
以前、教科書的な本で読んだのですが、卵は「需給が1%逼迫するだけで価格が5%(10%?)上昇する」というようなことが書いてありました。要は、需要と供給のバランスがちょっと崩れるだけで、価格はそれ以上に大きく変動するということです。
これは市場で価格が決まる農産物全体にいえることだと感じています。米についても、需要が減るか、供給が増えるかすれば、価格はいずれ落ち着くのではないでしょうか。ただしそれが今年なのか、数年後なのかはわかりません。