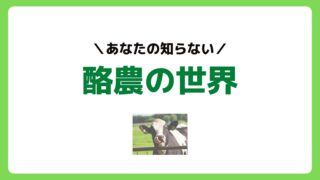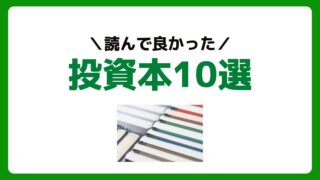読書系ポッドキャスト番組「ブックカタリスト」で知った本、
『Humankind 希望の歴史』(ルトガー・ブレグマン著)
を読みました。
一番の感想は「しばしば厭世的で性悪説に陥りがちな自分のような人こそ読んだ方がよい、人の善性を少し信じられるようになる本」というもの。
本書は次のような方におすすめです。
- 厭世的な方
- 性悪説に引っ張られがちな方
- 日々のネガティブなニュースに辟易している方
- 人類の良い側面に目を向けてみたい方
本書概要
- 「人間の本質は善である」ということを色々な側面から緻密に論考した本
- 内容
- 現実に起こった『蠅の王』での顛末、
- 世界大戦時に戦線にいた兵士たちの挙動、
- スタンフォード監獄実験など人の残酷性を知らしめた心理実験の疑わしさ、
- 人が悪に陥る時、
- 人の善性を取り戻すための10の行動指針、
- など多岐に渡るテーマを通して人の善性を説いている
- 著者:ルトガー・ブレグマン
- 文藝春秋
- 2021年発売
- ページ数:上巻272p、下巻270p
- 価格:上巻と下巻それぞれ1980円
本書を読んだきっかけ・理由
本書を読んだきっかけは、冒頭に書いたように読書系のポッドキャスト番組「ブックカタリスト」で本書が紹介されていたこと。
私自身、しばしば厭世的になります。
「世の中、尊敬できる人間なんて本当にごくごく少数しかいない。多くの大人が思慮に欠ける言動をとって各々が好き勝手なことばかりしている。」
強いストレスを抱えているときなど、このように感じることが少なくありません。
少し前に流行ったHSPという性格特性に私も該当するようで、神経過敏なため「人の負の側面」に目が向きやすいという自覚があります。
そのような自分でしたから、この本の内容を大まかに知った時には大変興味が沸きました。
ブックカタリスト内で語られていた内容だけでも、自分の認識を省みる良い機会となったからです。
印象的だった部分
- スタンフォード監獄実験やミルグラムの電気ショック実験はある種「結論ありきの操作された実験」だった
- 現実に起こった『蠅の王』と同じシチュエーションでは、小説内と真逆のことが起きた
- プラセボ効果の逆としてノセボ効果が存在する
- 偏見や憎しみは交流の欠如から生まれる。解決のためにはより多く交流すればよい
- 暴力的な抵抗運動よりも、非暴力的な抵抗運動の方がはるかに成功確率が高い
- 戦争においては、前線から遠く離れたところの人ほど相手への憎悪が強くなった
- ネガティビティバイアス(10の賛辞より1の不快な意見の方が心に強く残ってしまう)という認知バイアスの存在
- 人を疑わしく感じた時は「善意を想定する」ことで大抵うまくいく。なぜなら多くの人は善意で動いているから
- もっとたくさん質問をしよう
- 共感は人を消耗させるが、思いやりはエネルギーを生む。共感するのではなく思いやりを持とう
- ニュースは人をグループに括ったり腐ったリンゴに注目する。ニュースを避けよう
上記以外にもまだまだ無数にあります。
それほど考えさせられる点が多かったです。
雑感
本書を読んで抱いた雑多な感想は次のとおりです。
人の本質は善性ではないと思っていた
本書を読む前、たまに思い浮かぶことがあったのは、人の本質は「利己心に基づく無邪気な悪」なのではないかということ。
ですから、本書が「人の本質は善である」という内容だということを知った時には、そんなことはないだろうと反射的に思ってしまいました。
しかし、本書を読んで分かったのは、如何に自分がニュースなどからくるネガティビティバイアスに囚われていたかということ。
危険に敏感になって生き残ろうとする本能的な認知特性に、自分の場合はかなり振り回されていたのでしょう。
科学を絶対視できない
スタンフォード監獄実験やミルグラムの電気ショック実験は、人の残酷性を示した心理実験として大変に有名。
私も大学の心理学の講義で学びました。また、官僚制組織で人が思考停止に陥る論拠としてもこれらの実験が引き合いに出されることがあります。
そのため、これらの実験の非常に危うい裏側を検証した本書は、私にとってかなり衝撃的でした。
科学というと、大きくいえば「真理を解き明かしていくもの」だと思っています。
しかし、実験や検証の結果こそ世に知られど、その手法まで詳細に語られることは少ない気がします。その手法に致命的な欠陥があった場合、世に知れたその結果にどの程度の真実性があるでしょうか。
「科学的結果=真実」として語られていることも、決して絶対視することはできない。そのように感じました。
行動や認識が変わった
本書を読んだことで、ただなるほどなと頷くだけでは終わらず、実際に自分の行動や認識が多少なり変わりました。
具体的には次の3点。
- 人に対して懐疑的な気持ちが生じた時、できるだけ善意を想定するようになった
- ニュースや人から見聞きすることに共感するのではなく、思いやりの観点で捉えるようになった
- 本書で指摘されているとおり、共感して身動きが取れなくなるというよりも、「じゃあどうしてあげると良いか」という見方ができるようになった
- ニュースを見る頻度が減った
- 見るとしてもニュースの持つ特性に注意しながら見るようになった
実際の行動や認識にまで影響が及んだという点で、やはり本書を読んで良かったです。
人の善性を疑ってしまう人にこそ読んでほしい
繰り返しになりますが、
- 私のように何かと人に対して懐疑的な見方をしてしまうという人
- さらにいえば本心ではそうありたくないと感じている人
にこそ、より読んでほしいと強く思う本でした。
筆者の論考が完璧だとは思いませんし、気になる点が全くないということはありません。
それでも本書を読む価値は十分すぎるほどにある。そう思います。
教養を学ぶならオーディオブックや電子書籍が便利
教養を得たいと考えた場合、書店や図書館に紙の本を求めるのも当然良いのですが、自宅にいながら手軽に本を読む手段もあります。
- オーディオブック聴き放題サービス
- 電子書籍読み放題サービス
を利用することです。
いずれも、外に出かける必要がなく、すぐに読書ができるので大変便利です。
おすすめは以下4つのサービスです
いずれも聴き放題・読み放題の対象本がたくさんあります。
無料体験期間もあるので、短期集中で知識を身につけたいという人はぜひ活用してみてください。
↓Amazonのオーディオブックサービス「Audible」については、使ってみて非常に良かったので別途記事にしています